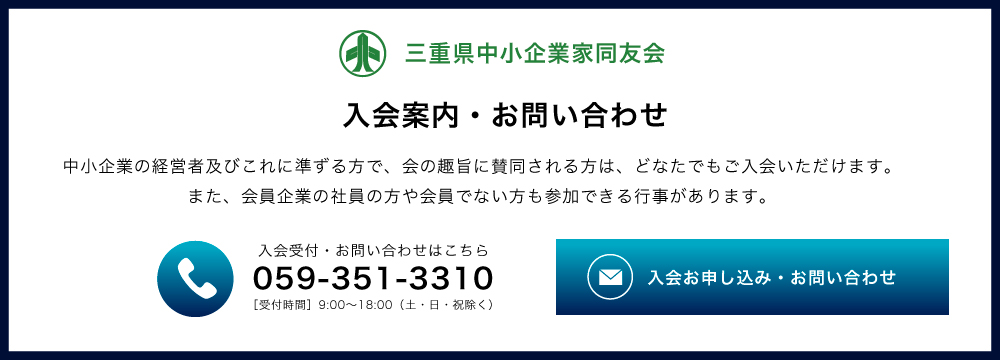社員と共に成長する経営とは? 前田テクニカに学ぶ「人を生かす」働き方改革
7月29日(火)19:00より、尾鷲商工会議所にて尾鷲グループ7月例会が開催されました。今回は、三重県菰野町で金属部品の製造を手掛ける株式会社前田テクニカの前田昌彦社長を報告者にお迎えし、「働き方の意識の変化に合わせた経営のあり方とは」をテーマにご報告いただきました。多くの企業が直面する人材確保や育成、働き方改革といった課題に対し、具体的な実践例と深い哲学に裏打ちされたお話は、参加者にとって大きな学びとなりました。



●理念で採用し、社員が主役の会社づくり
前田社長がまず強調されたのは、「人を活かす経営」の実践です。その出発点となるのが「採用」。かつては外国人技能実習生に頼った時期もありましたが、様々な課題に直面。その後、新卒採用へと舵を切りますが、当初は採用の仕組みがなく苦労されたそうです。
転機となったのは、あるプログラムへの参加を機に「理念で採用する」ことの重要性に気づいたことでした。同社が掲げる「希望・工夫・感謝」という三つの精神に心から共感してくれる人材を迎え入れる。これが、高い定着率を誇る現在の組織の土台となっています。驚くべきことに、採用活動の中心を担うのは若手社員。自社のウェブサイト企画や説明会のプレゼンテーションまで社員が主体的に行うことで、等身大の会社の魅力が求職者に伝わり、ミスマッチの少ない採用が実現しているのです。
●「やらされ感」から「やってる感」へ。社員の主体性を引き出す仕組み
人材育成においても、キーワードは「社員参画型」です。経営指針書は社長が作るものではなく、社員全員で会社の強みや弱みを分析し、共に未来を描くプロセスを大切にされています。
また、広報チーム「前田学ぶ」や、金属雑貨を開発・販売する自社商品プロジェクトKomonomono(コモノモノ)など、本業の製造業務とは異なる役割を社員に与えることで、個々の隠れた才能や強みを引き出しています。社長は企画から販売戦略まで社員に任せ、原則ノータッチ。こうした「任せる」姿勢が、社員の「やらされ感」を「やってる感」へと変え、自己肯定感を高めることに繋がっているのでしょう。
参加者アンケートでも、「本業以外の役割を与え、自己肯定感を高める取組みが印象的だった」「社員のことをしっかり見て、第一に経営されていると感じた」といった声が多数寄せられ、そのユニークな育成手法に多くの経営者が感銘を受けていました。

●「ワークインライフ」という視点。働きがいと生産性の両立
働き方改革においては、「『働き方改革』を『働かない改革』にしてはならない」という力強い言葉が印象的でした。年間休日125日に加え、有給取得率9割という実績の裏には、生産性向上への弛まぬ努力があります。定時後の電話対応をやめる、顧客と納期調整を積極的に行う、そして意図的に人員を増やして一人当たりの負荷を軽減するなど、具体的な施策を次々と実行。
前田社長は「ワークライフバランス」という言葉から一歩進み、「ワークインライフ(人生の中の仕事)」という考え方を提唱します。仕事は人生を豊かにするための一部であり、社員の人生そのものを引き受ける覚悟が経営者には必要だと語られました。
この深い哲学と具体的な実践に対し、参加者からは「たくさんの取組を時間がないことを言い訳にせず、ひとつひとつ実行されていることに自分自身の甘さを反省した」「どのお話も腹落ちする内容で、とても勉強になった」との感想が聞かれました。
今回の例会は、社員が辞めない、そして成長し続ける組織をいかにして作るか、その本質に迫る貴重な学びの場となりました。