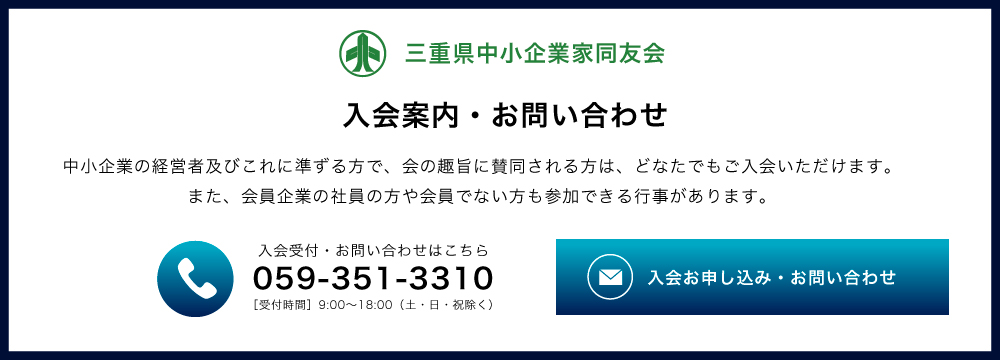8月8日(金)同友会事務局にて「三重県中小企業家同友会・東海財務局津財務事務所 意見交換会」を開催いたしました。

当日は、同友会の西村代表理事、平松代表理事をはじめとする経営者と、津財務事務所の石田所長をはじめとする方々が一堂に会し、地域経済の担い手として奮闘する中小企業経営者の「生の声」を直接届けるともに、地域経済の活性化に向けて様々な意見や議論が交わされました。

世界経済の波から身近な悩みまで。中小企業を取り巻く厳しい現実
会議の冒頭、津財務事務所から三重県内の経済情勢について財務事務所の景況調査をもとに「景気は持ち直している」との報告がありました。しかし、参加した経営者からは、日々の経営で直面しているより複雑で厳しい現実が語られました。
「米国の関税政策やEVシフトの不透明感で、自動車関連の金型受注が激減し、売上が半減した仲間もいる。グローバルな動きに、地域の中小企業は直接的な打撃を受けている」
「物価高騰は止まらない。でも、大手の購買担当者になかなか価格転嫁を認めてもらえない。賃上げは社会の流れとして理解しているが、原資がないのが本音。」
さらに、最低賃金が上昇しても、「年収の壁」を気にして働く時間を調整するパート従業員が多いという問題も指摘されました。結果的に世帯収入は増えず、企業の社会保険料負担だけが増加するというジレンマ。政府の賃上げ方針と現場の厳しい現実との間に横たわる深い溝や、マクロ経済の指標だけでは見えてこない、現場の切実な悩みが浮き彫りになりました。

「将来性を見てほしい!」金融機関に求める“本当の伴走支援”とは
次に大きなテーマとなったのが、事業の生命線ともいえる金融機関との関係性です。コロナ禍を乗り越え、新たな挑戦をしようとする企業にとって、その支援は不可欠です。
「将来性のあるプロジェクトで、大手企業との長期契約もある。それなのに、融資の相談をすると『追加で不動産担保を…』と言われてしまう。なぜ、新しい挑戦をするスタートアップにはリスクを取って『出資』するのに、地元の既存企業には担保を求めるのか。私たちの事業の可能性を、本当に見てくれているのだろうか?」
この問いかけは、多くの経営者が抱える共通の悩みです。金融機関には、単にお金を貸すだけでなく、企業の事業計画そのものを深く理解し、共に成長を目指す「伴走型支援」が求められています。財務事務所の方々も、この切実な声に真剣な表情で耳を傾けていました。

一歩先へ!「情報交換」から「地域活性化」への挑戦
この意見交換会では、同友会と金融機関が連携して地域を盛り上げるための「地域活性化協議会」の取組についても議論が交わされました。協議会の現状として「お互いに気を遣い、当たり障りのない情報交換で終わってしまっている」という厳しい自己評価もなされた一方で、「単なる情報交換で終わらせず、具体的なアクションにつなげていきたい」「金融機関の方々にももっと当事者として関わってほしい」といった前向きな意見も出され、より踏み込んだ議論が展開されました。
「中小企業が抱える価格転嫁の悩みを、発注元である大企業の購買担当者にも理解してもらう。そんなセミナーを国や金融機関主導で開催できないか」
このような具体的な提案も上がり、非常に建設的な議論となりました。
事業承継やM&Aといった地域の喫緊の課題についても、金融機関が「収益源」として見るのではなく、地域の未来を支えるという視点で関わってほしいという熱い要望も出されました。

今回の意見交換会を通じて、中小企業が直面する課題の根深さと、それを乗り越えようとする経営者の熱い思いを再確認することができました。こうした現場の「ホンネ」を国の機関と共有し、共に解決策を探っていくことこそが、三重県の経済を本当に元気にする第一歩です。
三重同友会では、これからも地域の皆さんと共に、より良い地域の未来を創るための活動を続けていきます。