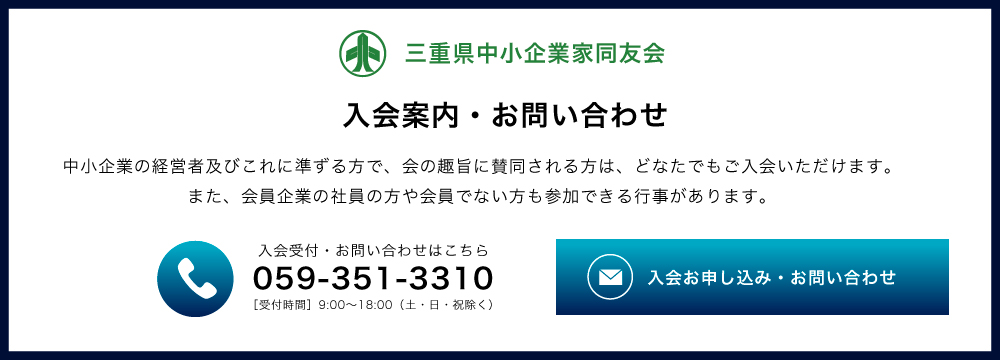10月30日木曜日に社員教育委員会より、社員定着セミナーが開催されました。

――株式会社ヒラマツ・平松洋一郎氏に学ぶ、多様な人材が共に育つ職場づくり
今回のセミナーでは、株式会社ヒラマツ代表取締役社長・平松洋一郎氏を講師に迎え、「社員の定着」をテーマに開催されました。
1951年創業の同社は、大型車両用洗浄機や各種部品の製造販売を手がける一方、福祉事業(就労支援事業を含む)にも取り組む企業です。平松氏は2013年に3代目社長として就任し、多様な人材を活かしながら「共に育つ組織」づくりを実践されています。
—
1.経営方針と多様な人材の活用
社長就任当初は「利益最優先」で苦労したという平松氏。
同友会での学びを通じて経営指針を成文化し、「共に育つ組織」への変化を目指すようになったと話します。
特に印象的だったのは、製造業でありながら福祉事業を併設している点。
2015年には就労支援事業を併設した介護施設「虹の夢 津」を、2022年には自律訓練事業所「トモニス」を開設。
就労支援B型からA型を経て、現在は正社員として工場で勤務している方もいるそうです。
また、社員の声に耳を傾けた柔軟な制度も特徴的。
例えば、子どもが3歳になるまでの社員に特別有給休暇(5日または10日)を付与したり、主婦層に向けた「中抜け」勤務制度を導入するなど、“働きやすさ”を社員の視点から設計しています。
—
2.外国人材の受け入れと定着
2017年からはベトナム技能実習生の受け入れを開始。
「稼ぎたい」という実習生の想いに寄り添い、仕事が少ない時期でも週4時間の日本語勉強会(残業代支給)を実施しています。
その結果、兄弟や夫婦で働くケースも増え、現在では約5組が勤務しているとのこと。
さらに、外国人社員にも経営指針書を配付し、自動翻訳を活用して共有。
一方で、制度的なリスクや責任問題の経験からも、“対話の大切さ”を学んだといいます。
「日本人でも外国人でも、個性がある。結局はどこまで対話ができるかが大事」と語る平松氏の言葉が印象的でした。
—
3.共通言語と心理的安全性の醸成
社員定着のカギとして、会社と社員の間に共通の目的(共通言語)を持つことの重要性を強調。
同社では決算書などの財務情報を社員と共有し、「儲かる」とはどういう状態かを一緒に考える取り組みを行っています。
採用ではスキルよりも「心理的安全性」や「安心感」を重視。
経営指針を公開し、職場の雰囲気を見てもらったうえで採用することで、入社後のギャップを防いでいます。
また、「人手不足」という言葉を社内では使わないという姿勢も印象的。
その言葉が社員に“負担”として伝わることを避け、ポジティブな共通言語で職場を整える姿勢が見えました。
—
4.業務効率化と企業の認知向上
営業活動の効率化として、顧客自身がウェブ上で洗浄機の見積もりを自動作成できるシステムを導入。
また、新型洗車機「ロボ洗」でグッドデザイン賞ベスト100を受賞するなど、社会的な評価や地域での認知度も高めています。
地元バスへのラッピング広告も、社員のモチベーション向上につながっているといいます。
—
5.グループ討論で見つめ直す「自社の定着」
セミナー後半では、「定着に向けた自社での取り組みと課題」をテーマにしたグループ討論が行われました。
参加者同士が自社の現状を共有し、“自社にとっての定着”とは何かを改めて考える時間に。
現場に持ち帰って実践するためのヒントが詰まった、有意義な学びの場となりました。
—
平松氏の実践から見えてきたのは、【制度ではなく“人を想う姿勢”こそが定着を生む】ということ。
多様な人が共に働き、成長していく。その基盤には「対話」「安心感」「共通言語」がある。
そんな“温かい経営”の在り方を感じたセミナーでした。