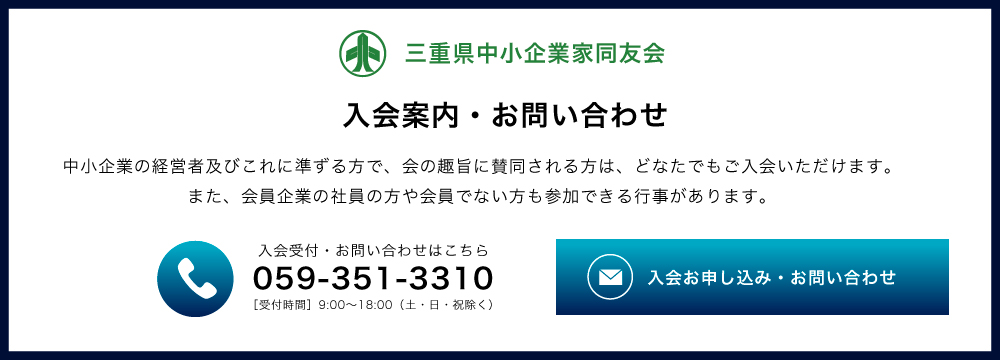9月10日(水)18:30よりプラトンホテル四日市にて、北勢支部9月例会が開催されました。今回の例会では、東北大学 特任教授の竹上嗣郎氏をお招きし、深刻化する人材不足のリスクに対し、「採用活動における自社の現状認識から始め 将来のミスマッチを防ぎ定着を図るためには を考えよう」をテーマに、参加者77名と共に深く学びあいました。

講演では、まず「人材リスクは経営リスク」であるとの認識が示され、企業に求められるのは、自社に現在どのような人材が在籍しているかを正確に把握し、理想とする人材像との間にどのようなギャップがあるかを明確にすることであると強調されました。急な人材不足といった「有事」に備えるためには、「平時の取り組みが重要」であると警鐘を鳴らし、経営者自身が現在雇用している人材の実態、構成、キーパーソンを把握し、採用面接のあり方やDX人材の確保についても考える必要性を提起されました。
また、「地元で働く」ことの魅力を高めるための多角的な視点が提供されました。
- 働く側(若手)の立場からは、「自分に向いている仕事が分からないまま就職してしまった」という現状や、コロナ禍を経て「働く場所はどこでも選択できる時代」になったこと、スキルアップを求めて転職を繰り返す傾向、安定志向(公務員志望)の高まり、SNS全盛期における地元でのリアルな繋がりの希薄化などが提示されました。
- 地元に就職する主な理由としては、家族・親族の近くで暮らしたい、馴染みのある土地での安心感、地元への愛着、都市部より生活費が安いといった理由が挙げられる一方、「仕事とプライベートを両立させたいから」という理由が意外と少ないことが指摘されました。
- 逆に地元に就職しない主な理由としては、給料への不安、新しい場所でのチャレンジ志向、地元企業の認知度不足、地元ではスキルアップできないという懸念が挙げられ、社会人として地元で暮らすイメージが十分に持てないことが、人材の県外流出につながっている可能性が示唆されました。特に三重県では、15歳から29歳の年齢層の転出超過が約8割を占めており、愛知県との人の移動が多いことや大学進学者収容力の低さも転出の根本要因として挙げられました。

●活発なグループ討論と成果
例会は全体で3部構成の形で進行しました。
- 「自社の人材棚卸しとリスク分析」**を個社でセルフワークする時間。
- 「リスクへの対応と課題、解決策の議論」**として、グループディスカッションを実施。ここでは、「自社の人材棚卸しとリスク分析」「リスクへの対応と課題、解決策の議論」「出てきた課題への対応策についてのさらなるディスカッション」がテーマとなりました。
- 「グループごとの議論紹介と講評」。
特に、県庁や銀行など外部のサポーターの方々にも議論をお聞きいただき、県内の中小企業が抱える人材課題の実態や本音を知り、今後の支援策検討に役立てていただく貴重な機会となりました。
参加者からは、
- 「皆さま率直に話していただき、やろうとしていることに勇気をいただきました」
- 「選ばれる会社となるため、地域貢献やブランディング、ホームページなど出来ることから進めていきたい」
- 「いつ何が起こるか分からない危機感をいただきました!具体的に掘り下げて、早期にトライ&エラーを繰り返して組織を活性化していきたい」
- 「後継者のなるべく早く育成することを心がける」
- 「まず人材の棚卸しをし、誰かが抜けたら会社が回らない事はないのかチェックします」
- 「業者は違えども人材に関する課題は共通していることが多い。人材とDXが繋がっているので、今後の本業支援営業の強化に役立てたい」
- 「退職よりも、病欠や介護、育休などの対応策」
- 「仕事の引き継ぎの準備」「業務の見える化を図る事で極力属人化を避ける」 といった、具体的な学びや今後の行動に繋がる前向きな声が多く寄せられ、産官金連携による相互理解の深化が図られた点も注目すべき点です。

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。今回の例会で得られた知見や課題意識を活かし、各企業が未来の人材戦略を描き、地域を活性化していくための一助となれば幸いです。
今後も北勢支部では、実践者の声に触れ、学び合える例会を企画してまいります。次回のご参加もお待ちしています!